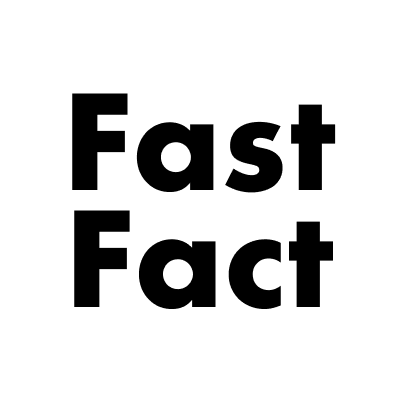【参本会議】舟山康江参議院議員会長が災害対策基本法等改正案に対する質疑

舟山康江参議院議員会長(参議院議員/山形県)は25日、参議院本会議において、災害対策基本法等改正案に対する質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。
令和7年4月25日
災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する質問
国民民主党・新緑風会
舟山 康江
国民民主党・新緑風会の舟山康江です。
会派を代表して、災害対策基本法等の一部を改正する法律案について、関係各大臣に質問を致します。
我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、 土砂災害、地震、津波、火山噴火など様々な災害に見舞われやすい国土となっています。 とりわけ今世紀に入り、災害が巨大化、頻発化、多様化、複合化しており、対応は待ったなしです。
自然災害の発生自体を防ぐことは困難ですが、発生時の被害軽減は可能です。そのために、これまでも累次に渡り様々な対策を講じ、法制度の整備・見直し、体制強化を図ってきましたが、未だに課題山積です。 昨年1月の能登半島地震の教訓等を踏まえて、災害対策基本法や災害救助法等の見直しが行われようとしていますが、今般の改正でどの程度課題解決に結びつくのか、他の課題提起も含めて質問します。
1. 自治体への役割集中の是正について
災害発生時には、避難の指示や誘導、避難所の開設、必要な物資の調達・運搬、住居の手当や医療・保健、福祉の提供など、様々な対応が不可欠ですが、平時は民間が担う役割も含めてほぼ全ての業務が自治体に集中します。人員削減等で職員数の減少が進む中、わずかな自治体職員でこれらの対応に当たるのは困難を極めます。
今般の改正案では、国による地方公共団体に対する支援体制の強化が盛り込まれていますが、今指摘したような構造的問題の解決に必要な抜本的な改善策を教えて下さい。「餅は餅屋」、平時から民間も含めた役割分担の仕組みや、友好都市との連携のあり方について、平時からの準備が必要であり、その体制整備を後押しすべきではないでしょうか。坂井防災担当大臣にお伺いします。
2. 避難所の環境改善について
先日、今から95年前、昭和5年の北伊豆地震時の避難所の写真を見ましたが、今の避難 所と全く変わらない有様に驚きました。
避難所の環境整備が指摘され続けている中で、基本法には自治体に「被災者の生活環境の整備に必要な措置」を講じる努力義務が規定されていますが、「被災者の生活環境」としてどのような水準を確保することを期待しているのでしょうか。石破総理は、就任直後の所信表明でも「災害関連死ゼロを実現すべく、避難所の満たすべき基準を定めたスフィア基準も踏まえつつ避難所の在り方を見直す」と決意を述べていますが、劣悪な環境の改善が進まない理由と具体的な改善策について坂井大臣お答え下さい。
3. 災害関連死の防止・救済に向けた対策について
避難所においては、一人あたりの適切な居住面積の確保と併せ、プライベート空間の創出、温かい食事の提供等への配慮が欠かせません。これまでは、「緊急時だから仕方がない」「雨風がしのげるだけマシ」「温かい食事などわがまま、あるだけありがたいと思え」というような暗黙の空気感が漂っていたと感じます。
このような環境改善は、近年課題となっている「災害関連死」の防止にも直結すると考えますが、この災害関連死について、その要因分析と近年の特徴、予防策について、防災担当大臣の認識を伺います。
また、災害関連死の認定基準が自治体によってばらつきがあり、認定を行う審査会の設置根拠となる条例の規定がない自治体もあります。認定基準の統一に向けた対策についても、 坂井大臣に伺います。
4. 女性や子どもの視点に立った対策推進の必要性について
災害対応全般に共通しますが、女性や子どもなどの弱者に配慮する視点がこれまで不十分だったことが、避難所の環境整備が遅れてきた背景の一つにあると考えます。 内閣府男女共同参画局は、令和2年5月に「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」を発出しています。このガイドラインは、東日本大震災などの災害を踏まえ、人口の半分以上を占める女性の視点が活かされていないとの観点から、平時の段階から発災後の避難所や応急住宅での対応に始まり復旧・復興に至るまでの全ての過程での、様々な留意点を指摘しています。
こうした女性の人権につながる重要な指摘を含むガイドラインが、先般の能登半島地震では活かされなかったとの指摘がなされています。
大災害の度ごとに、避難所や仮設住宅で、女性や子どもがないがしろにされる対応が繰り返されてきています。
災害対策基本法には、女性、子どもの文言がありません。この度の法改正において、内閣府策定のガイドラインや、能登半島地震の現場での教訓がどのように反映されたのか、まさに本改正で欠けている部分ではないかと考えますが、改正案で対応がなされない理由と、今後どのようにガイドラインを踏まえ具体的に女性や子どもの被災地における人権、安全を守るよう取り組んでいくのか、坂井大臣の見解を伺います。
避難所の開設場所、仮設住宅の建設場所についても課題があると考えます。発生直後の一時避難所として、多くの場合学校の体育館等が活用されています。初期の避難場所としてはいいのですが、本来学校は教育の場であり、子どもの健全な成長に必要な場所です。いつまでもそこにとどまり続けるのではなく、できるだけ早期に環境の整った別の場所に移動できる支援を行うべきです。
また、仮設住宅も、場所の確保の問題等から学校の校庭・運動場に建設する例も見られますが、できるだけ避けるべきと考えます。被災後の教育環境の早期回復と避難所・仮設住宅の確保の両立をいかに図るか、坂井大臣に伺います。
5. ボランティアの活動に対する公的支援について
災害時における被災者支援や復旧復興に当たり、ボランティアの存在は不可欠であり、災害対策基本法にもその役割や環境整備、連携推進努力が明記されています。であればこそ、ボランティアの方々の活動に対する実費弁償についても、その考え方や公費負担の範囲について法律等に明記すべきと考えますが、いかがでしょうか?
現状は、炊き出しの際の食材費等の実費弁償は行われるものの、交通費補助は今年1月の補正予算でようやく期間限定で措置されましたが、宿泊費等は対象外です。厳しい環境の中、 被災者に寄り添い、懸命に活動するボランティアの皆様の活動に対しては、もう少し公的支援を厚くすべきと考えますが、坂井大臣の見解を伺います。
6. 生活再建に向けた支援策について
被災者の一日も早い生活再建を実現する上で、各種手当・給付金や、金融・税制面からの支援が欠かせませんが、その際、「災害救助法」の適用の有無が様々な公的支援制度が発動されるトリガーになっています。
災害救助法では、自治体ごとの住家等の被害数が、主たる適用の判断基準になっていますが、住家被害が大きくなくても事業への影響が甚大だったり、全体の規模が大きくなくても、被災者個人にとっては二重債務問題に直面するケースなど、規模の大小だけでは計れない事態も発生しています。
このような事態への対応として、もうひとつ、「生命・身体への危害又はその恐れが生じた場合」との基準も規定されていますが、適用を逡巡する傾向が指摘されています。法の目的である被災者の保護と社会の秩序の保全のためには、積極的な適用を促すべきではないでしょうか?
加えて、生活再建に向けた支援に当たっては、災害救助法の適用基準とは別の基準を設けるなど、被災者に寄り添ったきめの細かい対応が必要と考えますが、坂井大臣の見解をお伺いします。
7. 災害復旧事業の適用拡大について
災害時には、道路や河川、農地、公立学校など、公共性が高いものについては、極めて国庫補助率の高い、「災害復旧事業」を活用することができますが、鉄道については、「公共交通」と言われ、極めて公共性が高いにもかかわらず、この適用を受けることができず、災害をきっかけに運休が長引き、廃線に追い込まれる事例も見受けられます。
鉄道が対象外であることについては、「運賃収入を充てて事業の運営を行うべきものであるから」との答弁が返ってきますが、被災自体が不可抗力であり、「公共交通」としての位置づけであることから、とりわけ赤字路線についてさらなる配慮を行うべきではないか、改めて前向きな答弁を国土交通大臣に求め、質問を終わります。
以上

舟山康江参議院議員会長(参議院議員/山形県)は25日、参議院本会議において、災害対策基本法等改正案に対する質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。
令和7年4月25日
災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する質問
国民民主党・新緑風会
舟山 康江
国民民主党・新緑風会の舟山康江です。
会派を代表して、災害対策基本法等の一部を改正する法律案について、関係各大臣に質問を致します。
我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、 土砂災害、地震、津波、火山噴火など様々な災害に見舞われやすい国土となっています。 とりわけ今世紀に入り、災害が巨大化、頻発化、多様化、複合化しており、対応は待ったなしです。
自然災害の発生自体を防ぐことは困難ですが、発生時の被害軽減は可能です。そのために、これまでも累次に渡り様々な対策を講じ、法制度の整備・見直し、体制強化を図ってきましたが、未だに課題山積です。 昨年1月の能登半島地震の教訓等を踏まえて、災害対策基本法や災害救助法等の見直しが行われようとしていますが、今般の改正でどの程度課題解決に結びつくのか、他の課題提起も含めて質問します。
1. 自治体への役割集中の是正について
災害発生時には、避難の指示や誘導、避難所の開設、必要な物資の調達・運搬、住居の手当や医療・保健、福祉の提供など、様々な対応が不可欠ですが、平時は民間が担う役割も含めてほぼ全ての業務が自治体に集中します。人員削減等で職員数の減少が進む中、わずかな自治体職員でこれらの対応に当たるのは困難を極めます。
今般の改正案では、国による地方公共団体に対する支援体制の強化が盛り込まれていますが、今指摘したような構造的問題の解決に必要な抜本的な改善策を教えて下さい。「餅は餅屋」、平時から民間も含めた役割分担の仕組みや、友好都市との連携のあり方について、平時からの準備が必要であり、その体制整備を後押しすべきではないでしょうか。坂井防災担当大臣にお伺いします。
2. 避難所の環境改善について
先日、今から95年前、昭和5年の北伊豆地震時の避難所の写真を見ましたが、今の避難 所と全く変わらない有様に驚きました。
避難所の環境整備が指摘され続けている中で、基本法には自治体に「被災者の生活環境の整備に必要な措置」を講じる努力義務が規定されていますが、「被災者の生活環境」としてどのような水準を確保することを期待しているのでしょうか。石破総理は、就任直後の所信表明でも「災害関連死ゼロを実現すべく、避難所の満たすべき基準を定めたスフィア基準も踏まえつつ避難所の在り方を見直す」と決意を述べていますが、劣悪な環境の改善が進まない理由と具体的な改善策について坂井大臣お答え下さい。
3. 災害関連死の防止・救済に向けた対策について
避難所においては、一人あたりの適切な居住面積の確保と併せ、プライベート空間の創出、温かい食事の提供等への配慮が欠かせません。これまでは、「緊急時だから仕方がない」「雨風がしのげるだけマシ」「温かい食事などわがまま、あるだけありがたいと思え」というような暗黙の空気感が漂っていたと感じます。
このような環境改善は、近年課題となっている「災害関連死」の防止にも直結すると考えますが、この災害関連死について、その要因分析と近年の特徴、予防策について、防災担当大臣の認識を伺います。
また、災害関連死の認定基準が自治体によってばらつきがあり、認定を行う審査会の設置根拠となる条例の規定がない自治体もあります。認定基準の統一に向けた対策についても、 坂井大臣に伺います。
4. 女性や子どもの視点に立った対策推進の必要性について
災害対応全般に共通しますが、女性や子どもなどの弱者に配慮する視点がこれまで不十分だったことが、避難所の環境整備が遅れてきた背景の一つにあると考えます。 内閣府男女共同参画局は、令和2年5月に「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン~」を発出しています。このガイドラインは、東日本大震災などの災害を踏まえ、人口の半分以上を占める女性の視点が活かされていないとの観点から、平時の段階から発災後の避難所や応急住宅での対応に始まり復旧・復興に至るまでの全ての過程での、様々な留意点を指摘しています。
こうした女性の人権につながる重要な指摘を含むガイドラインが、先般の能登半島地震では活かされなかったとの指摘がなされています。
大災害の度ごとに、避難所や仮設住宅で、女性や子どもがないがしろにされる対応が繰り返されてきています。
災害対策基本法には、女性、子どもの文言がありません。この度の法改正において、内閣府策定のガイドラインや、能登半島地震の現場での教訓がどのように反映されたのか、まさに本改正で欠けている部分ではないかと考えますが、改正案で対応がなされない理由と、今後どのようにガイドラインを踏まえ具体的に女性や子どもの被災地における人権、安全を守るよう取り組んでいくのか、坂井大臣の見解を伺います。
避難所の開設場所、仮設住宅の建設場所についても課題があると考えます。発生直後の一時避難所として、多くの場合学校の体育館等が活用されています。初期の避難場所としてはいいのですが、本来学校は教育の場であり、子どもの健全な成長に必要な場所です。いつまでもそこにとどまり続けるのではなく、できるだけ早期に環境の整った別の場所に移動できる支援を行うべきです。
また、仮設住宅も、場所の確保の問題等から学校の校庭・運動場に建設する例も見られますが、できるだけ避けるべきと考えます。被災後の教育環境の早期回復と避難所・仮設住宅の確保の両立をいかに図るか、坂井大臣に伺います。
5. ボランティアの活動に対する公的支援について
災害時における被災者支援や復旧復興に当たり、ボランティアの存在は不可欠であり、災害対策基本法にもその役割や環境整備、連携推進努力が明記されています。であればこそ、ボランティアの方々の活動に対する実費弁償についても、その考え方や公費負担の範囲について法律等に明記すべきと考えますが、いかがでしょうか?
現状は、炊き出しの際の食材費等の実費弁償は行われるものの、交通費補助は今年1月の補正予算でようやく期間限定で措置されましたが、宿泊費等は対象外です。厳しい環境の中、 被災者に寄り添い、懸命に活動するボランティアの皆様の活動に対しては、もう少し公的支援を厚くすべきと考えますが、坂井大臣の見解を伺います。
6. 生活再建に向けた支援策について
被災者の一日も早い生活再建を実現する上で、各種手当・給付金や、金融・税制面からの支援が欠かせませんが、その際、「災害救助法」の適用の有無が様々な公的支援制度が発動されるトリガーになっています。
災害救助法では、自治体ごとの住家等の被害数が、主たる適用の判断基準になっていますが、住家被害が大きくなくても事業への影響が甚大だったり、全体の規模が大きくなくても、被災者個人にとっては二重債務問題に直面するケースなど、規模の大小だけでは計れない事態も発生しています。
このような事態への対応として、もうひとつ、「生命・身体への危害又はその恐れが生じた場合」との基準も規定されていますが、適用を逡巡する傾向が指摘されています。法の目的である被災者の保護と社会の秩序の保全のためには、積極的な適用を促すべきではないでしょうか?
加えて、生活再建に向けた支援に当たっては、災害救助法の適用基準とは別の基準を設けるなど、被災者に寄り添ったきめの細かい対応が必要と考えますが、坂井大臣の見解をお伺いします。
7. 災害復旧事業の適用拡大について
災害時には、道路や河川、農地、公立学校など、公共性が高いものについては、極めて国庫補助率の高い、「災害復旧事業」を活用することができますが、鉄道については、「公共交通」と言われ、極めて公共性が高いにもかかわらず、この適用を受けることができず、災害をきっかけに運休が長引き、廃線に追い込まれる事例も見受けられます。
鉄道が対象外であることについては、「運賃収入を充てて事業の運営を行うべきものであるから」との答弁が返ってきますが、被災自体が不可抗力であり、「公共交通」としての位置づけであることから、とりわけ赤字路線についてさらなる配慮を行うべきではないか、改めて前向きな答弁を国土交通大臣に求め、質問を終わります。
以上