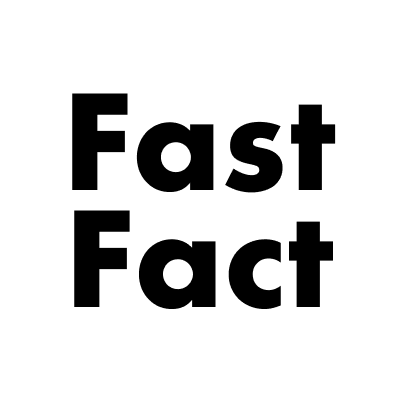【参本会議】伊藤孝恵議員が教職員給与特措法改正案に対する質疑

伊藤孝恵広報委員長(参議院議員/愛知県)は21日、参議院本会議で議題となった教職員給与特措法改正案に対する質疑を行った。質疑の全文は以下のとおり。
令和7年5月21日
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する質疑
国民民主党・新緑風会 伊藤孝恵
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。私は会派を代表し、冒頭、総理に伺います。
「コメは買ったことがない」「売るほどある」この発言が、農水大臣を辞表提出に至らしめるほどの力があると咄嗟に感じなかったのであれば、総理には我が国に立ち込める政治不信や、スーパーの店頭で物価高騰に吐息する、国民の顔が見えていないと言わざるを得ません。
江藤農水大臣の事実上の更迭理由および、一時は厳重注意で続投を決めた判断との齟齬について、ご説明下さい。
次に、ただいま議題となりました法律案について、令和元年の給特法改正に対する評価から伺います。当時、萩生田文科大臣は、長時間労働で疲弊する学校現場に向け、「これは言わば“応急処置”として、勤務時間かどうかを超えて、校務に従事している時間を在校等時間と位置付け、まずは時間外の在校等時間を月45時間・年360時間という上限をターゲットとして、縮減する仕組みを提案した」と述べられ、法改正後に指針を策定されました。
しかし令和4年度、文科省が行った教員勤務実態調査に基づく推計によれば、時間外在校等時間が月45時間を超える割合は、小学校で6割強、中学校で8割弱に上っています。結局、大半の教員が長時間労働を続けています。
それどころか5年半前より事態は悪化しており、精神疾患による病気休職者は令和5年度に7,119人と過去最多を更新しました。公立学校の教員採用倍率も低下傾向に歯止めがかからず、令和6年度の小学校の倍率は過去最低の2.2倍です。こうした実態を踏まえたとき、果たして、令和元年改正は「応急処置」として適切だったと言えるのか、総理の見解を伺います。
また萩生田大臣は、処遇に関しても「抜本的な見直しをして、教員の皆さんが誇りを持って仕事ができる環境をしっかりつくっていきたい」と答弁されました。伴って、参議院文教科学委員会の附帯決議では、「3年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、本法その他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること」としました。
しかし今回、政府提出の改正案による教職調整額は令和8年から段階的に1%ずつ引き上げ、10%に到達するのは6年後の令和13年だといいます。余りに貧弱、且つ危機感が感じられない内容です。
総理は、今回の改正案をもって「抜本的な見直し」と捉えているのか、「誇りを持って仕事ができる環境を作ることができた」とお考えになっているのか、伺います。併せて、教員の長時間労働の解消には、給特法の廃止を含む見直しが必要と考えますが、先行する国立付属学校の評価と併せて、総理の見解を伺います。
「ところで本当にそれは、先生の仕事ですか?」
学校における働き方改革を進めるには、私たちは、この問いを幾度も重ねていかねばなりません。
校内清掃や部活動、学校給食費や教材費が未納の保護者に対して電話や文書で督促し、時に家庭訪問までして徴収・管理する。総理、本当に、それは先生の仕事ですか?
小中学校のいじめの認知件数は2023年、71万1,633件になりました。約10年で4.1倍、暴力行為の発生件数は10万3,626件で2.2倍です。
教室の中にいる被害者と加害者、双方の学ぶ権利を守り、主張が食い違う保護者の敵対を解消するための専門的な介入をする。総理、本当にそれは、先生の仕事ですか?
日本語指導が必要な児童生徒数は6万2,099人、約10年で1.8倍。ポルトガル語、中国語、フィリピノ語、スペイン語、ベトナム語。年々多様化する言語に対し、日本語指導アドバイザーや母語支援員の確保が追い付かない中で、母文化を尊重した教育と保護者対応が求められる。総理、本当にそれは、先生の仕事ですか?
不登校児童生徒数は34万6,482人、約10年で2.8倍。特別支援学級に在籍する児童生徒数は36万8,847人で2倍。通級による指導を受けている児童生徒数は19万6,288人で2.3倍を超える中、変わりゆく学校現場の課題に対応しようと、過去10年で施行された学校や教職員に対する新たな義務、又は努力義務を課した法律は議員立法14本、閣法6本の計20本です。
教員が授業準備や児童・生徒との対話ではなく、国や教育委員会、自治体等からの調査書の記入に多くの時間を割かれる。総理、本当にそれは、先生の仕事ですか?
OECD(経済協力開発機構)の国際教員指導環境調査によれば、日本の先生の最大のストレスは「事務的な業務が多すぎること」次に「保護者の懸念に対処すること」であり、いづれも調査参加国の平均を大きく上回っています。
カナダでは2012年から、ドイツでは2015年から「1‐in/1‐out」が導入され、行政手続きを1つ増やすなら1つ減らすことが法令上、義務化されています。アメリカは2017年から「1‐in/2‐out」です。
総理に伺います。学校における教員の事務作業や、学習指導要領、生徒指導提要の改訂時には「1‐in/2‐out」を導入すべきと考えますが、ご所見をお聞かせください。
加えて、イギリスでは1998年および2003年に政府が「教師が請け負うべきでない仕事」の一覧、例えば、生徒や保護者からの集金や大量の印刷、出欠管理、試験監督やICTのトラブル対応などを明示し、教師は授業や学習に集中できるようサポートを受けるべきであり、専門知識を擁していない事務を教師に求めることは不適切であると原則化しました。2023年には更に、給食時の対応や医療同意アンケートの管理、保護者や生徒への過大な情報共有、いわく生徒からのハラスメントやモンスターペアレント対応も教師の仕事ではないと通知しました。働き方改革がいつまで経っても実現しない日本との差は、政府の本気度に他なりません。
文部科学省は従来、学校や教師が担ってきた業務について、「基本的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の「3分類」に基づき見直しを図ってきましたが、教育委員会による取組の実施率が5割を超えたのは、3分類14項目のうち半数以下の6項目に留まっています。
2019年に「3分類」が策定されてから、既に6年が経過しています。業務の見直しが十分に進まない理由と、「3分類」の再検討と厳格化の必要性について、総理の認識をお聞かせ下さい。また、イギリスの例にならい、我が国においても文科省が「教師が請け負うべきでない仕事」の具体例を明示、通知すると共に、これらの業務を代わりに担う人材と予算を、国の責任で確保していく必要があると考えますが、総理の見解を伺います。
先ずは、学校だけでは解決が難しい事案については、行政が保護者等から直接相談を受けるなど、新たな支援体制の構築を指針に位置づけるのが第一歩と考えますが、総理の見解をお聞かせください。
本法案では、教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画等の策定と公表などが義務付けられましたが、民間では昨今、女性管理職比率や男性育休取得率など、人的資本の情報開示により、自社の透明性や信頼性を高めることで投資を呼び込み、採用に繋げています。
今後、学校現場に人材を招き入れたいのであれば、自治体の標準職務表を共通フォーマットで作成し、教員一人当たりの持ち授業時数の上限を設定し、もちろん校務DXを推進した上で、教員を支えるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教員業務支援員や部活動指導員など、専門スタッフの配置を拡充していく必要があります。それに加えて、育休や介護休の取得率や勤務間インターバルの導入状況などを公表する、そこまでやって初めて民間と競争できるスタートラインに立てるのではないでしょうか。総理のご所見を伺います。
就職氷河期世代の採用についても伺います。氷河期世代が大学を卒業した西暦2000年前後は、教員採用試験倍率が著しく高く、教員免許を取得したものの、教員になれなかった者が数多くいます。私もその1人です。
社会の理不尽や、様々な職業を経験した氷河期世代は、子ども達に語りかける言葉を数多く有しています。
総理は、先月25日に開催した、第1回「就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」において、就職氷河期世代を教員として積極的に採用するための検討を関係閣僚に指示したと承知しています。いつまでに検討を終え、どの程度の採用が可能と考えているのか、教えて下さい。
最後に。これまでの政治や行政、地域社会や保護者、もしかしたら教員自身も、1人の先生に対し、あまりにも多くのことを求めすぎていたのではないでしょうか?
「ところで本当にそれは、先生の仕事ですか?」
内省と提案の参議院での審議を、今日も日本中の学び舎で子ども達に伴走する先生方に届けることを自誓して、私の質問を終わります。
以上

伊藤孝恵広報委員長(参議院議員/愛知県)は21日、参議院本会議で議題となった教職員給与特措法改正案に対する質疑を行った。質疑の全文は以下のとおり。
令和7年5月21日
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する質疑
国民民主党・新緑風会 伊藤孝恵
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。私は会派を代表し、冒頭、総理に伺います。
「コメは買ったことがない」「売るほどある」この発言が、農水大臣を辞表提出に至らしめるほどの力があると咄嗟に感じなかったのであれば、総理には我が国に立ち込める政治不信や、スーパーの店頭で物価高騰に吐息する、国民の顔が見えていないと言わざるを得ません。
江藤農水大臣の事実上の更迭理由および、一時は厳重注意で続投を決めた判断との齟齬について、ご説明下さい。
次に、ただいま議題となりました法律案について、令和元年の給特法改正に対する評価から伺います。当時、萩生田文科大臣は、長時間労働で疲弊する学校現場に向け、「これは言わば“応急処置”として、勤務時間かどうかを超えて、校務に従事している時間を在校等時間と位置付け、まずは時間外の在校等時間を月45時間・年360時間という上限をターゲットとして、縮減する仕組みを提案した」と述べられ、法改正後に指針を策定されました。
しかし令和4年度、文科省が行った教員勤務実態調査に基づく推計によれば、時間外在校等時間が月45時間を超える割合は、小学校で6割強、中学校で8割弱に上っています。結局、大半の教員が長時間労働を続けています。
それどころか5年半前より事態は悪化しており、精神疾患による病気休職者は令和5年度に7,119人と過去最多を更新しました。公立学校の教員採用倍率も低下傾向に歯止めがかからず、令和6年度の小学校の倍率は過去最低の2.2倍です。こうした実態を踏まえたとき、果たして、令和元年改正は「応急処置」として適切だったと言えるのか、総理の見解を伺います。
また萩生田大臣は、処遇に関しても「抜本的な見直しをして、教員の皆さんが誇りを持って仕事ができる環境をしっかりつくっていきたい」と答弁されました。伴って、参議院文教科学委員会の附帯決議では、「3年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、本法その他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること」としました。
しかし今回、政府提出の改正案による教職調整額は令和8年から段階的に1%ずつ引き上げ、10%に到達するのは6年後の令和13年だといいます。余りに貧弱、且つ危機感が感じられない内容です。
総理は、今回の改正案をもって「抜本的な見直し」と捉えているのか、「誇りを持って仕事ができる環境を作ることができた」とお考えになっているのか、伺います。併せて、教員の長時間労働の解消には、給特法の廃止を含む見直しが必要と考えますが、先行する国立付属学校の評価と併せて、総理の見解を伺います。
「ところで本当にそれは、先生の仕事ですか?」
学校における働き方改革を進めるには、私たちは、この問いを幾度も重ねていかねばなりません。
校内清掃や部活動、学校給食費や教材費が未納の保護者に対して電話や文書で督促し、時に家庭訪問までして徴収・管理する。総理、本当に、それは先生の仕事ですか?
小中学校のいじめの認知件数は2023年、71万1,633件になりました。約10年で4.1倍、暴力行為の発生件数は10万3,626件で2.2倍です。
教室の中にいる被害者と加害者、双方の学ぶ権利を守り、主張が食い違う保護者の敵対を解消するための専門的な介入をする。総理、本当にそれは、先生の仕事ですか?
日本語指導が必要な児童生徒数は6万2,099人、約10年で1.8倍。ポルトガル語、中国語、フィリピノ語、スペイン語、ベトナム語。年々多様化する言語に対し、日本語指導アドバイザーや母語支援員の確保が追い付かない中で、母文化を尊重した教育と保護者対応が求められる。総理、本当にそれは、先生の仕事ですか?
不登校児童生徒数は34万6,482人、約10年で2.8倍。特別支援学級に在籍する児童生徒数は36万8,847人で2倍。通級による指導を受けている児童生徒数は19万6,288人で2.3倍を超える中、変わりゆく学校現場の課題に対応しようと、過去10年で施行された学校や教職員に対する新たな義務、又は努力義務を課した法律は議員立法14本、閣法6本の計20本です。
教員が授業準備や児童・生徒との対話ではなく、国や教育委員会、自治体等からの調査書の記入に多くの時間を割かれる。総理、本当にそれは、先生の仕事ですか?
OECD(経済協力開発機構)の国際教員指導環境調査によれば、日本の先生の最大のストレスは「事務的な業務が多すぎること」次に「保護者の懸念に対処すること」であり、いづれも調査参加国の平均を大きく上回っています。
カナダでは2012年から、ドイツでは2015年から「1‐in/1‐out」が導入され、行政手続きを1つ増やすなら1つ減らすことが法令上、義務化されています。アメリカは2017年から「1‐in/2‐out」です。
総理に伺います。学校における教員の事務作業や、学習指導要領、生徒指導提要の改訂時には「1‐in/2‐out」を導入すべきと考えますが、ご所見をお聞かせください。
加えて、イギリスでは1998年および2003年に政府が「教師が請け負うべきでない仕事」の一覧、例えば、生徒や保護者からの集金や大量の印刷、出欠管理、試験監督やICTのトラブル対応などを明示し、教師は授業や学習に集中できるようサポートを受けるべきであり、専門知識を擁していない事務を教師に求めることは不適切であると原則化しました。2023年には更に、給食時の対応や医療同意アンケートの管理、保護者や生徒への過大な情報共有、いわく生徒からのハラスメントやモンスターペアレント対応も教師の仕事ではないと通知しました。働き方改革がいつまで経っても実現しない日本との差は、政府の本気度に他なりません。
文部科学省は従来、学校や教師が担ってきた業務について、「基本的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の「3分類」に基づき見直しを図ってきましたが、教育委員会による取組の実施率が5割を超えたのは、3分類14項目のうち半数以下の6項目に留まっています。
2019年に「3分類」が策定されてから、既に6年が経過しています。業務の見直しが十分に進まない理由と、「3分類」の再検討と厳格化の必要性について、総理の認識をお聞かせ下さい。また、イギリスの例にならい、我が国においても文科省が「教師が請け負うべきでない仕事」の具体例を明示、通知すると共に、これらの業務を代わりに担う人材と予算を、国の責任で確保していく必要があると考えますが、総理の見解を伺います。
先ずは、学校だけでは解決が難しい事案については、行政が保護者等から直接相談を受けるなど、新たな支援体制の構築を指針に位置づけるのが第一歩と考えますが、総理の見解をお聞かせください。
本法案では、教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置実施計画等の策定と公表などが義務付けられましたが、民間では昨今、女性管理職比率や男性育休取得率など、人的資本の情報開示により、自社の透明性や信頼性を高めることで投資を呼び込み、採用に繋げています。
今後、学校現場に人材を招き入れたいのであれば、自治体の標準職務表を共通フォーマットで作成し、教員一人当たりの持ち授業時数の上限を設定し、もちろん校務DXを推進した上で、教員を支えるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教員業務支援員や部活動指導員など、専門スタッフの配置を拡充していく必要があります。それに加えて、育休や介護休の取得率や勤務間インターバルの導入状況などを公表する、そこまでやって初めて民間と競争できるスタートラインに立てるのではないでしょうか。総理のご所見を伺います。
就職氷河期世代の採用についても伺います。氷河期世代が大学を卒業した西暦2000年前後は、教員採用試験倍率が著しく高く、教員免許を取得したものの、教員になれなかった者が数多くいます。私もその1人です。
社会の理不尽や、様々な職業を経験した氷河期世代は、子ども達に語りかける言葉を数多く有しています。
総理は、先月25日に開催した、第1回「就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」において、就職氷河期世代を教員として積極的に採用するための検討を関係閣僚に指示したと承知しています。いつまでに検討を終え、どの程度の採用が可能と考えているのか、教えて下さい。
最後に。これまでの政治や行政、地域社会や保護者、もしかしたら教員自身も、1人の先生に対し、あまりにも多くのことを求めすぎていたのではないでしょうか?
「ところで本当にそれは、先生の仕事ですか?」
内省と提案の参議院での審議を、今日も日本中の学び舎で子ども達に伴走する先生方に届けることを自誓して、私の質問を終わります。
以上