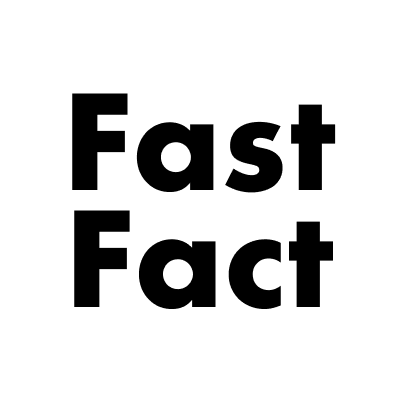【衆本会議】仙田晃宏議員が環境影響評価法改正案について質疑

仙田晃宏国対副委員長(衆議院議員/岐阜3区)は8日、衆議院本会議で議題となった環境影響評価法改正案について質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。
国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。
昨年10月の第50回衆議院議員選挙にて初当選させていただき、本日初めて登壇の機会をいただきました。
衆議院議員になって迎える初のゴールデンウイークは、国政報告会や後援会の立ち上げ、駅頭での挨拶や、街頭演説、地元のお祭りや例大祭等への出席を通じ、地元の皆様の声を聞いてまいりました。
皆様から頂くお声の大半は、「トランプ関税」と「物価高」の2点です。
トランプ関税について、日本時間の5月2日にアメリカと交渉されたと伺っております。国民民主党は関税の引き下げの交渉材料に農産物を使用しないよう提言させていただいておりますが、現在の交渉状況および、今後の妥結点や着地見込み・見通しについて、赤澤経済再生担当大臣にお伺いいたします。(経済再生担当大臣)
次に「物価高」についてお伺いします。国民の皆様の大半のお声は「お米」と「ガソリン」価格の高騰です。お米について、備蓄米を放出しているにもかかわらず、5キロ4200円程度と価格が下がっておりません。また「ガソリン」については、暫定税率廃止ではなく、補助金を活用し、1リットル当たり10円下げると表明されております。
ゴールデンウイークもガソリン代が高いから近場ですまそうと、せっかくおでかけを楽しみにしている長期休暇ですら国民の皆様は我慢している状況です。「働き控え」に続き、「お出かけ控え」をしているこの状況を政府はどうお考えでしょうか?昨年12月11日に自民党と公明党、国民民主党の3党の幹事長間でガソリンの暫定税率の廃止に関する合意書を締結したはずです。その存在はどこにいってしまったのでしょうか?(経済産業大臣)
国民民主党の主張は、「とって配るなら最初からとるな!」です。1リットル当たり10円を引き下げではなく、1日も早く暫定税率の廃止を強く求めます。武藤経済産業大臣にお伺いします。ガソリン価格を10円引き下げにした根拠はなんでしょうか?なぜ10円なのでしょうか?また、暫定税率の廃止はいつ実現して頂けるのでしょうか?(経済産業大臣)
明確な答弁を求め、本題である、環境影響評価法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。
まず初めに、エネルギー政策についてお伺いいたします。2023年度の我が国における発電方式の割合は、火力発電が約68.6%、再生可能エネルギーが約22.9%、原子力発電は約8.5%を占めております。
これに対して、資源エネルギー庁は2040年度の電源構成について、再生可能エネルギーで4割から5割程度、原子力で2割程度、火力発電で3割から4割程度を見込んでおります。2040年度に向けたエネルギー基本計画は順調でしょうか、また進捗状況について武藤経済産業大臣にお伺いいたします。(経済産業大臣)
また、こうした目標に向け、本法律案が、再生可能エネルギーの導入加速に資するものとお考えでしょうか、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、事業者負担の軽減についてお伺いいたします。本法律案は、建替後の事業の位置が大きく変わらないことを前提に、配慮書手続について、記載事項の一部を簡略化するものであります。環境配慮を確保しつつ、制度について合理化を図っていくことは必要であり、こうした取組は、再エネ施設や火力発電所等のリプレースの促進につながり、脱炭素や経済活性化にも資するものと考えられます。
ただ、本法律案による見直しは配慮書の内容に限定されており、配慮書の作成を含めた一連の手続は現行のまま維持されることから、発電所の建替に係るリードタイム短縮への効果は限定的ではないかと考えます。そこで本法律案における措置で、事業者負担の軽減策は十分とお考えなのか、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、事業者に応じた政府の対応についてお伺いいたします。自然環境への配慮に係る対応は開発事業者によって大きな差があるのが現状であります。環境保護団体の調査では、稼働中の風力発電、アセスメント手続中の風力発電のいずれにおいても、バランスよく環境への配慮を行っている企業がある一方で、顕著に自然環境への配慮を欠いている企業の存在も指摘されております。
こうした実態を踏まえますと、環境への配慮を欠く企業に対しては、厳正に対処する必要があると考えます。そのような企業に対し、何らかのペナルティを科すべきと考えますが、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、法対象になる前に設置された風力発電への対応についてです。環境影響評価手続件数が最も多いのが風力発電事業であり、同事業は2012年から環境影響評価法の対象とされております。
風力発電の耐用年数は20年程度とされていることから、今回の改正法施行後、対象となるのは、当面の間、2012年以前に設置された設備の建替事業が中心となります。そのため、法に基づく環境影響評価の手続きを経ていない可能性があり、適切な立地検討や環境影響の調査がなされていないおそれもあります。
それにもかかわらず、本法律案では、建替事業の要件を満たす場合、事業実施区域の概況調査などを省略できるとされており、適切な環境配慮がなされているのかどうか懸念が残ります。
そこで、風力発電が環境影響評価法の対象となる前に設置された設備の建替事業に関しても、建替事業の要件を満たす場合に配慮書の記載事項を簡略化することの妥当性について、浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
次に、陸上風力のアセス対象の基準についてお伺いいたします。現行の環境影響評価法では、事業規模が大きいほうが一般的に環境への影響も大きいとの考えから、一定規模以上の開発事業を対象として環境アセスメントを求めております。
2021年10月、環境省は、陸上風力の第一種事業の対象を、1万kW以上から5万kW以上に引き上げました。しかしながら、陸上風力発電の環境影響は、単に風車の数や大きさのみならず、立地などのほかの要素も大きく影響いたします。風力発電については、例えば、住宅地に隣接していたり、希少な野鳥の生息地に近い場合など、小規模な事業であっても環境への影響が大きくなることがあります。
また、環境影響評価の対象とならない小規模な事業であっても、複数の事業者が一定地域に集中して事業を行うことで、結果として大規模な開発となり、累積的な環境影響を及ぼす可能性があるのではないでしょうか。こうした場合における政府の対応について浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、火力発電のリプレース事業における環境負荷についてお伺いいたします。火力発電は高効率化が進んでいて、リプレースにより、出力が大きくなることも考えられ、政令の内容次第では、本法律案における建替えの対象にならない可能性があります。
国として、2050年カーボンニュートラルという大きな目標を掲げ、温室効果ガスの排出削減に向けて取り組む中においては、環境負荷が増えないことがリプレースの前提になると考えるべきではないでしょうか。そのためには、容量出力規模ベースではなく、CO2、NOXなどの環境負荷が増えていないかどうかで判断すべきではないでしょうか。浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
次に、アセス図書の継続公開についてお伺いいたします。本法律案により、アセス手続に関する文書である「アセス図書」を、環境大臣が継続的に公開することになります。せっかく作成した環境影響に係る資料であり、周辺の複数の事業による累積的な環境影響を把握するためにも、ぜひとも有効に活用すべきものと思います。
一方で、図書を公開した事業者に事後的に過度な負担等、たとえば第三者からの頻繁な問い合わせへの対応などが生じることのないように、制度化にあたっての運用方法等についても丁寧に検討していただきたく思いますが、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、国におけるアセス図書の活用方針についてお伺いいたします。環境影響評価図書には、環境影響や生物調査に係る貴重なデータが含まれており、事業の実施以外にも、研究促進や技術向上に活用することが期待できます。
そこで、図書の情報を公開するにとどまらず、将来のアセスメント手続への利用や手続の効率化を念頭に、例えばデジタル情報として整備する、環境分野におけるオープンデータベースにアセス図書から得られる情報を反映させるなど、積極的に活用していくことについて、浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
次に、本法律案の原子力リプレースについてお伺いいたします。本法律案における建替事業は原子力発電所も対象になり得ると考えられますが、原子力発電所に関するリプレースの定義についてお伺いいたしたく存じます。
増設という定義になってしまうとゼロから立ち上げていかないといけなく、手続きの効率化が図られないと思いますが浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
最後に、現行の環境アセスメント制度の課題についてお伺いいたします。環境アセスメント制度は、事業者の自主性を尊重しつつ、一定の基準を押しつけるのではなく、事業者自身による、よりよい環境に向けた取組を促進する、環境政策上の重要なツールであると考えております。この制度が、今後とも、より効率的・効果的なものとなるよう改善していくべきと考えますが、環境省の考える、改正事項に含まれなかった現行制度の課題と今後の対応方針について浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
国民民主党は、国民生活に現実的に向き合う改革中道政党です。政府が策定した第7次エネルギー基本計画に対し、エネルギーの安全保障、電力の安定供給の確保および地球温暖化対策のための施策を盛り込むよう求めました。これらの政策の実現のため、本法律案が重要な推進力となることを期待し、私の質問を終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

仙田晃宏国対副委員長(衆議院議員/岐阜3区)は8日、衆議院本会議で議題となった環境影響評価法改正案について質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。
国民民主党・無所属クラブの仙田晃宏です。
昨年10月の第50回衆議院議員選挙にて初当選させていただき、本日初めて登壇の機会をいただきました。
衆議院議員になって迎える初のゴールデンウイークは、国政報告会や後援会の立ち上げ、駅頭での挨拶や、街頭演説、地元のお祭りや例大祭等への出席を通じ、地元の皆様の声を聞いてまいりました。
皆様から頂くお声の大半は、「トランプ関税」と「物価高」の2点です。
トランプ関税について、日本時間の5月2日にアメリカと交渉されたと伺っております。国民民主党は関税の引き下げの交渉材料に農産物を使用しないよう提言させていただいておりますが、現在の交渉状況および、今後の妥結点や着地見込み・見通しについて、赤澤経済再生担当大臣にお伺いいたします。(経済再生担当大臣)
次に「物価高」についてお伺いします。国民の皆様の大半のお声は「お米」と「ガソリン」価格の高騰です。お米について、備蓄米を放出しているにもかかわらず、5キロ4200円程度と価格が下がっておりません。また「ガソリン」については、暫定税率廃止ではなく、補助金を活用し、1リットル当たり10円下げると表明されております。
ゴールデンウイークもガソリン代が高いから近場ですまそうと、せっかくおでかけを楽しみにしている長期休暇ですら国民の皆様は我慢している状況です。「働き控え」に続き、「お出かけ控え」をしているこの状況を政府はどうお考えでしょうか?昨年12月11日に自民党と公明党、国民民主党の3党の幹事長間でガソリンの暫定税率の廃止に関する合意書を締結したはずです。その存在はどこにいってしまったのでしょうか?(経済産業大臣)
国民民主党の主張は、「とって配るなら最初からとるな!」です。1リットル当たり10円を引き下げではなく、1日も早く暫定税率の廃止を強く求めます。武藤経済産業大臣にお伺いします。ガソリン価格を10円引き下げにした根拠はなんでしょうか?なぜ10円なのでしょうか?また、暫定税率の廃止はいつ実現して頂けるのでしょうか?(経済産業大臣)
明確な答弁を求め、本題である、環境影響評価法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。
まず初めに、エネルギー政策についてお伺いいたします。2023年度の我が国における発電方式の割合は、火力発電が約68.6%、再生可能エネルギーが約22.9%、原子力発電は約8.5%を占めております。
これに対して、資源エネルギー庁は2040年度の電源構成について、再生可能エネルギーで4割から5割程度、原子力で2割程度、火力発電で3割から4割程度を見込んでおります。2040年度に向けたエネルギー基本計画は順調でしょうか、また進捗状況について武藤経済産業大臣にお伺いいたします。(経済産業大臣)
また、こうした目標に向け、本法律案が、再生可能エネルギーの導入加速に資するものとお考えでしょうか、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、事業者負担の軽減についてお伺いいたします。本法律案は、建替後の事業の位置が大きく変わらないことを前提に、配慮書手続について、記載事項の一部を簡略化するものであります。環境配慮を確保しつつ、制度について合理化を図っていくことは必要であり、こうした取組は、再エネ施設や火力発電所等のリプレースの促進につながり、脱炭素や経済活性化にも資するものと考えられます。
ただ、本法律案による見直しは配慮書の内容に限定されており、配慮書の作成を含めた一連の手続は現行のまま維持されることから、発電所の建替に係るリードタイム短縮への効果は限定的ではないかと考えます。そこで本法律案における措置で、事業者負担の軽減策は十分とお考えなのか、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、事業者に応じた政府の対応についてお伺いいたします。自然環境への配慮に係る対応は開発事業者によって大きな差があるのが現状であります。環境保護団体の調査では、稼働中の風力発電、アセスメント手続中の風力発電のいずれにおいても、バランスよく環境への配慮を行っている企業がある一方で、顕著に自然環境への配慮を欠いている企業の存在も指摘されております。
こうした実態を踏まえますと、環境への配慮を欠く企業に対しては、厳正に対処する必要があると考えます。そのような企業に対し、何らかのペナルティを科すべきと考えますが、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、法対象になる前に設置された風力発電への対応についてです。環境影響評価手続件数が最も多いのが風力発電事業であり、同事業は2012年から環境影響評価法の対象とされております。
風力発電の耐用年数は20年程度とされていることから、今回の改正法施行後、対象となるのは、当面の間、2012年以前に設置された設備の建替事業が中心となります。そのため、法に基づく環境影響評価の手続きを経ていない可能性があり、適切な立地検討や環境影響の調査がなされていないおそれもあります。
それにもかかわらず、本法律案では、建替事業の要件を満たす場合、事業実施区域の概況調査などを省略できるとされており、適切な環境配慮がなされているのかどうか懸念が残ります。
そこで、風力発電が環境影響評価法の対象となる前に設置された設備の建替事業に関しても、建替事業の要件を満たす場合に配慮書の記載事項を簡略化することの妥当性について、浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
次に、陸上風力のアセス対象の基準についてお伺いいたします。現行の環境影響評価法では、事業規模が大きいほうが一般的に環境への影響も大きいとの考えから、一定規模以上の開発事業を対象として環境アセスメントを求めております。
2021年10月、環境省は、陸上風力の第一種事業の対象を、1万kW以上から5万kW以上に引き上げました。しかしながら、陸上風力発電の環境影響は、単に風車の数や大きさのみならず、立地などのほかの要素も大きく影響いたします。風力発電については、例えば、住宅地に隣接していたり、希少な野鳥の生息地に近い場合など、小規模な事業であっても環境への影響が大きくなることがあります。
また、環境影響評価の対象とならない小規模な事業であっても、複数の事業者が一定地域に集中して事業を行うことで、結果として大規模な開発となり、累積的な環境影響を及ぼす可能性があるのではないでしょうか。こうした場合における政府の対応について浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、火力発電のリプレース事業における環境負荷についてお伺いいたします。火力発電は高効率化が進んでいて、リプレースにより、出力が大きくなることも考えられ、政令の内容次第では、本法律案における建替えの対象にならない可能性があります。
国として、2050年カーボンニュートラルという大きな目標を掲げ、温室効果ガスの排出削減に向けて取り組む中においては、環境負荷が増えないことがリプレースの前提になると考えるべきではないでしょうか。そのためには、容量出力規模ベースではなく、CO2、NOXなどの環境負荷が増えていないかどうかで判断すべきではないでしょうか。浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
次に、アセス図書の継続公開についてお伺いいたします。本法律案により、アセス手続に関する文書である「アセス図書」を、環境大臣が継続的に公開することになります。せっかく作成した環境影響に係る資料であり、周辺の複数の事業による累積的な環境影響を把握するためにも、ぜひとも有効に活用すべきものと思います。
一方で、図書を公開した事業者に事後的に過度な負担等、たとえば第三者からの頻繁な問い合わせへの対応などが生じることのないように、制度化にあたっての運用方法等についても丁寧に検討していただきたく思いますが、浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
次に、国におけるアセス図書の活用方針についてお伺いいたします。環境影響評価図書には、環境影響や生物調査に係る貴重なデータが含まれており、事業の実施以外にも、研究促進や技術向上に活用することが期待できます。
そこで、図書の情報を公開するにとどまらず、将来のアセスメント手続への利用や手続の効率化を念頭に、例えばデジタル情報として整備する、環境分野におけるオープンデータベースにアセス図書から得られる情報を反映させるなど、積極的に活用していくことについて、浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
次に、本法律案の原子力リプレースについてお伺いいたします。本法律案における建替事業は原子力発電所も対象になり得ると考えられますが、原子力発電所に関するリプレースの定義についてお伺いいたしたく存じます。
増設という定義になってしまうとゼロから立ち上げていかないといけなく、手続きの効率化が図られないと思いますが浅尾環境大臣の見解をお伺いいたします。(環境大臣)
最後に、現行の環境アセスメント制度の課題についてお伺いいたします。環境アセスメント制度は、事業者の自主性を尊重しつつ、一定の基準を押しつけるのではなく、事業者自身による、よりよい環境に向けた取組を促進する、環境政策上の重要なツールであると考えております。この制度が、今後とも、より効率的・効果的なものとなるよう改善していくべきと考えますが、環境省の考える、改正事項に含まれなかった現行制度の課題と今後の対応方針について浅尾環境大臣にお伺いいたします。(環境大臣)
国民民主党は、国民生活に現実的に向き合う改革中道政党です。政府が策定した第7次エネルギー基本計画に対し、エネルギーの安全保障、電力の安定供給の確保および地球温暖化対策のための施策を盛り込むよう求めました。これらの政策の実現のため、本法律案が重要な推進力となることを期待し、私の質問を終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。