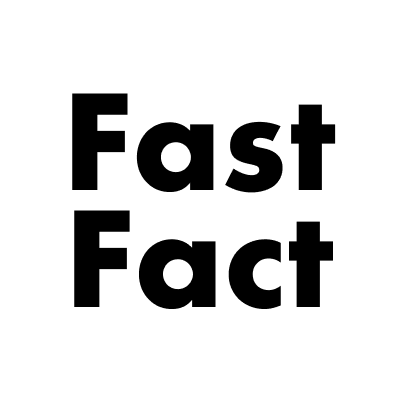【岩屋外務大臣】冒頭、私(岩屋大臣)から3点ご報告がございます。
まず、新ローマ教皇レオ14世の選出についてでございます。
現地時間の5月8日、新ローマ教皇レオ14世台下(だいか)が選出されたことに対しまして、日本政府として、心からお祝いを申し上げたいと思います。
バチカンは、約14億人のカトリック教徒を背景にして、国際社会において強い発信力を有しております。我が国としても、新教皇の下で、バチカンとの良好な関係を一層発展させてまいりたいと思います。
冒頭発言
新ローマ教皇レオ14世台下の選出
日印、日・パキスタン外相電話会談
【岩屋外務大臣】次に、日印、日・パキスタンの外相電話会談についてでございます。
カシミール情勢を受けまして、7日、インドのジャイシャンカル外務大臣と電話会談を行いました。また、先刻、パキスタンのダール副首相兼外務大臣とも電話会談を行いました。
双方との会談では、私(岩屋大臣)から、まず、テロはいかなる理由によっても正当化できないと、あらゆる形態のテロ行為を断固として避難をすると、また、カシミールで発生したテロ事件についても、公正な調査と犯罪者の処罰が必要であるということを伝えました。
また、一連の事態によりまして、インド・パキスタン双方において、民間人に犠牲が出ていると、子供も含まれているということを大変痛ましく思います。更なる報復の応酬を招き、エスカレートすることを強く懸念しているということを伝えました。
我が国としては、南アジアの平和と安定のために、インド及びパキスタン双方が自制して、対話を通じて事態を安定化させることを、引き続き、求めてまいります。
日・ヨルダン外相会談
【岩屋外務大臣】最後に、日・ヨルダン外相会談です。この後、ヨルダンのサファディ副首相兼外務・移民大臣と外相会談を実施する予定でございます。
ヨルダンは、中東地域の安定の要であり、我が国の重要なパートナーでございます。
サファディ外相とは、日本とヨルダンの戦略的パートナーシップの強化に向けた一層の連携を改めて確認したいと思います。加えて、ガザ情勢への対応や、二国家解決及び長期的な地域の平和と安定の確立に向けた連携を更に強化してまいります。
冒頭、私(岩屋大臣)からは以上です。
米国による関税措置に関する米英間の貿易合意(日本の方針)
【共同通信 阪口記者】米国の関税措置についてお尋ねします。米国と英国の両政府が、昨日、貿易の合意に達しました。米国側は、セクター別の関税措置の引下げで合意し、日本が米国との関税交渉で目指す成果と一致する部分があると思います。世界経済に米国の関税措置が影響を与える中で、こうした交渉の実績が積み重なっていくこと自体への受け止めを伺います。一方で、自動車への関税が10%というのは、残る形となったので、米国の強硬姿勢も垣間見えると思います。トヨタ自動車の決算が悪化する見通しだとも発表されましたけれども、今後、どのように交渉を続けるお考えなのか、合意を急ぐ考えなのかどうかも併せて、お尋ねします。
【岩屋外務大臣】米国時間で言いますと、8日、米国と英国との間の貿易合意が発表されたと承知しております。しかし、他国の動向について、逐一コメントすることは控えたいと思います。
いずれにしても、日米間では、双方が率直かつ建設的な姿勢で協議に臨み、可能な限り早期に合意して、首脳間で発表できるようにしようということでは一致しているわけでございます。
我が国としては、これまでの日米協議の結果も踏まえて、引き続き、政府一丸となって、最優先かつ全力で取り組んでいきたいと考えております。
その上で、あえて申し上げれば、各国の置かれた立場や状況は様々でございますから、米国との協議のスケジュール、あるいは合意の内容、タイミング、これが異なってくるのは当然だと思っております。
我が国としては、これまで2回、赤澤交渉代表による協議が行われたわけですけれども、3回目の協議に向けて、政府一丸となって、取り組んでまいりたいと考えております。
中国による軍事的威圧
【日経新聞 馬場記者】中国の、領海や領空への侵入について伺います。今月3日には、中国海警局のヘリコプターが、尖閣周辺の日本領空を侵犯し、日中双方が抗議し合う事態となりました。尖閣周辺の領海への接近事案も続いています。中国とは、経済関係の改善を図る一方で、中国による日本周辺での軍事的威圧は強化されてきているようにも思います。この状況をどうご覧になっているか、また、事態がエスカレーションしないために、日本政府として、どう中国に向き合うべきだと考えられるかをお伺いします。
【岩屋外務大臣】3日、尖閣諸島周辺の我が国領海に、中国海警船4隻が侵入するとともに、その領海内に侵入した中国海警船から発艦したヘリコプター1機が、我が国領空を侵犯したことは、極めて遺憾であります。同日(3日)、中国側に対して、極めて厳重に抗議をいたしました。また、再発防止を強く求めたところです。
政府としては、国民の生命・財産、我が国の領土・領空・領海、これを断固として守るという方針の下に、引き続き、緊張感を持って関係省庁間で連携して、情報収集に努めるとともに、尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を期してまいりたいと思っております。
中国との間では、安全保障に関するものも含めまして、数多くの課題や懸案がありますが、価値を共有する同盟国や同志国との連携を前提としながら、「戦略的互恵関係」を包括的に推進するとともに、「建設的で安定的な関係」の構築を目指していきたいと、これが政府としての一貫した方針でございます。
こういう大きな方向性の下に、日中安保対話などによる、安全保障分野における平素からの意思疎通も含めて、幅広い分野で意思疎通を一層深めていきたいと、そして、課題や懸案を一つずつ減らすと、協力できる分野を一つずつ増やしていくという努力を、これからも続けていきたいと考えております。
NPT運用検討会議第3回準備委員会
【中国新聞 中川記者】NPTの準備委員会について伺います。日本政府がまとめた軍縮・不拡散教育の共同声明について、前回22年の声明にあった核兵器の使用による「壊滅的な人道上の結末」という文言が削られました。その理由と、原爆の惨禍をめぐる表現の後退についての大臣の受け止めを伺います。また、前回は賛同した米国が、今回、声明に加わらなかった受け止めについても併せて伺います。
【岩屋外務大臣】御指摘のステートメントは、軍縮と不拡散に関する教育が、「核兵器のない世界の実現」という目標を推進するための有用かつ効果的な手段であることを強調し、国際社会に対して、軍縮・不拡散教育の促進を訴えるものでございます。
今回のステートメントでは、本年が被爆80年であるということに言及し、「核兵器の使用による、短期・長期的な、壊滅的かつ多面的な影響とその帰結」に関する知識の蓄積が、軍縮・不拡散教育に貢献してきたことに触れております。
その上で、「核爆発とその後の壊滅的な被害を経験した人々の貴重な証言が世界中の軍縮教育の取組の中で不可欠な役割を果たしてきた」ことや、「人々の記憶を保存し、将来の世代に伝えるように奨励」することなど、これまで以上に、様々な観点を入れ込んだところでございます。
したがって、前回と表現が違うからといって、これが後退したという指摘は当たらないと考えております。
それから、今回のステートメントに係わる調整過程をつまびらかにすることは控えたいと思いますし、個別の国の対応について評価することも差し控えることが適当だと考えておりますけれども、米国を始めとする関係国との間では、来年の運用検討会議に向けて、引き続き連携していくことを確認しております。
なお、今回のステートメントをしっかり提出した準備委員会に参加した国の数は、96か国でございまして、過去最多でございます。そういう意味では、機運が徐々に高まってきていると、日本も、そのことに貢献してきているということを、申し上げることはできようかと思います。
岸田総理特使のインドネシア訪問
【トリビューン・ニュース スシロ記者】5月4日夕方、元総理大臣岸田文雄氏は、インドネシア・プラボウォ大統領公邸に訪問しました。岸田氏は、石破首相からの手紙を大統領に直接渡しました。その手紙の内容の一つは、AZEC、アジア・ゼロエミッション・コミュニティ・プロジェクトに関するものと、元総理が話しました。石破首相からの手紙の内容は、何が書かれてあるんでしょうか。教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
【岩屋外務大臣】5月3日から5日まで、石破茂内閣総理大臣の特使及びアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)議員連盟最高顧問として、岸田文雄前総理・衆議院議員が、AZEC議連訪問団とともにインドネシア共和国を訪問いたしました。
岸田総理特使一行は、石破総理からの親書を手交の上、プラボウォ・インドネシア共和国大統領と会談をされております。
御指摘の親書の内容は、外交上のやり取りでございますので、つまびらかにすることは差し控えたいと思いますけれども、プラボウォ大統領との会談におきましては、今申し上げたAZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)の協力を更に推進するために、AZEC議連を設立したというお話ですとか、引き続き、インドネシアとともにAZECを発展させていく決意ということをお話をされたと伺っておりますので、親書も、そういったお話の中身に関連するものであったのではなかろうかと思っているところでございます。
日・パキスタン外相電話会談
【NHK 米津記者】冒頭の御発言に関連して伺います。パキスタンのダール外相との電話会談の中で、ダール外相側からは、どのようなお話があったのか、パキスタン側の立場の説明ですとか、どういったことがあったのか、可能な範囲で教えていただけますか。
【岩屋外務大臣】基本的に外交上のやり取りですから、詳細は控えさせていただきたいと思います。パキスタン政府が、これまで公に発表しておられる立場に沿った説明が詳しくありました。
いずれにしても、インドに対してもパキスタンに対しても、対話によって事態を沈静化・安定化させてほしいと、そうすべきだということを、しっかりとお伝えをしたところでございます。
ジョセフ・ナイ氏死去、ソフトパワーの活用
【朝日新聞 加藤記者】ジョセフ・ナイ氏の死去について伺います。4月に亡くなられたリチャード・アーミテージ氏に続き、日米関係に大きな影響を与えたナイ氏の訃報をどのように受け止めたでしょうか。ナイ氏は強制力によらず、文化や価値観を通じて影響を及ぼす「ソフトパワー」も提唱されましたが、現在の国際情勢を踏まえて、日本外交において、ソフトパワーをどう活用すべきとお考えか。
【岩屋外務大臣】ジョセフ・ナイ先生、私(岩屋大臣)も、もう何度もお目にかかってきました。先般亡くなられたアーミテージさんと一緒に、アーミテージ・ナイ・レポートというレポートを数次にわたって出しておられまして、私(岩屋大臣)も直接会って御指導いただいたこともございます。改めて、心からこれまでの御功績に敬意を表し、また哀悼の意を表したいと思っております。
ナイ先生といえば、今おっしゃったソフトパワーという言葉を編み出したというか、これを定着させた先生でございます。
今、日本は、例えば日本の歴史・伝統・文化はもとよりですけれども、最近のJ-POPであるとか、アニメであるとか、漫画であるとか、これが世界中の方々から、共感を得ていることを、私(岩屋大臣)も、海外に行くたびに直接感じてきておりますけれども、こういうものも、日本のソフトパワーの一つだなということを改めて感じているところでございます。
ナイ先生の、そういったお教えというか、御指導を大切にして、これからもソフトパワーも十分に発揮して、外交を展開していきたいと考えているところでございます。