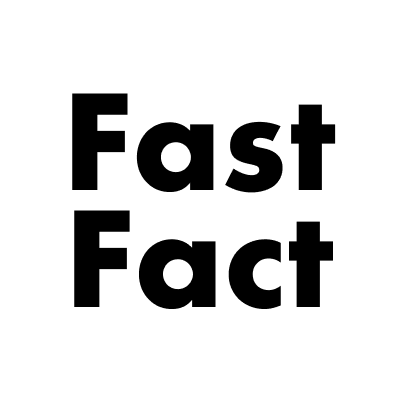【参本会議】田村まみ議員が公益通報者保護法改正案について質疑

田村まみ国民運動局長(参議院議員/全国比例)は14日、国民民主党を代表し、参議院本会議で議題となった公益通報者保護法改正案に対する質疑を行った。質疑の全文は以下のとおり。
令和7年5月14日
国民民主党・新緑風会
田村 まみ
公益通報者保護法改正案
本会議質問
国民民主党・新緑風会の田村まみです。会派を代表して質問いたします。
ただいま議題となりました(公益通報者保護法)は、事業者による食品偽装事件やリコール隠し事件など、国民の生命、身体、財産等に被害を及ぼす可能性がある違法行為が相次いだことを契機として平成18年に施行され令和4年に改正法が施行されています。
令和5年11月に消費者庁が行ったアンケート調査では、従業員数が三百人超千人以下の事業者に勤務する就業者の57.6%、5千人超の事業者であっても47.7%が内部通報制度を理解していないことが明らかになりました。制定から20年以上が経過しているにもかかわらず、このように公益通報者保護法に対する国民の理解は未だ進んでいるとは言い難い状況にあります。国民の理解が進み活用促進される改正になるべく質問いたします。
はじめに、公益通報者保護法の周知・活用が進まない要因とされる、対象法律の範囲と規定方式について伺います。
公益通報者保護法の第1条は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することが目的であると謳っております。
故に、公益通報の対象となる法律は国民の生命、身体、財産等の利益の保護を直接的な目的としている法律に限定されております。
国民の理解が進まない背景には、法律の目的と対象法律が一致していないと国民から受け止められていることがあるのではないでしょうか。法律の目的を厳格に解し、対象法律を狭めていることから、結果として法律の活用と通報者の保護が進んでいないものと思われますが、伊東大臣に見解を伺います。
石破政権が中小企業の賃上げ環境整備に向けての施策の1つとして掲げる、企業間取引における適切な価格転嫁の是正に向け、下請法等の改正が審議されています。
下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用は、公益通報者保護法の対象法令です。その認識が中小企業や発注側企業の交渉担当者に周知され活用されることは取引の適正化に有用と考えますが、活用が進んでいるといえません。活用状況と今後の対策について、伊東大臣にお尋ねします。
赤澤賃金向上担当大臣に伺います。6月までに策定を予定されている円滑な価格転嫁を含む賃上げ支援策の議論の中で、この公益通報者保護法の活用について検討されていますか。
中小企業庁の下請けかけこみ寺への個別相談が身バレの恐れにより芳しくなく、価格交渉促進月間アンケート調査の回収率もいまだ20%に満たない状況です。伊東大臣、公益通報者保護法で保護される対象範囲の狭さが影響しているとは考えませんか。
公益通報者保護法を真に実効性のある法律にするためには、単に消費者被害の防止という観点だけでなく、法令遵守を促し、労働者を含む内部告発者を守る制度として位置付け直し、対象法律や通報対象事実を包括的に捉え直すことが求められているのではないでしょうか。先に挙げた企業間取引における法令違反は対象ですが、現行法の別表に記載の無い価格転嫁を阻害する商慣習等を威圧的に求める行為、いわゆるハラスメントなど、法令上明確な罰則規定がなくとも、公益通報の対象とする方向で検討すべきではないでしょうか。伊東大臣の見解をお聞かせ下さい。
次に、事業者が従業員等からの公益通報に適切に対応するための内部通報体制整備義務について伺います。以下、伊東大臣に伺います。
今回の改正案では、現行法の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしております。その一方、体制整備義務自体はこれまでと同様、常時使用する従業員数が300人超の事業者に限られ、300人以下の事業者については努力義務のままです。消費者庁の実態調査によれば、従業員数300人以下の事業者が内部通報制度を導入していない理由として、「努力義務にとどまるから」が48.9%と、最も多く挙げられています。
国民への周知を徹底するためには、従業員数300人以下の事業者による体制整備を義務化することが効果的だと思われますが、義務化は必要ないのですか、政府の見解をお聞かせ下さい。
小規模ゆえの人材を含む資源の乏しさから中小企業への体制整備義務化は困難という意見は承知しています。その課題への対応は、大企業と同じ形ではない手段を検討しつつ義務化を進めるべきではないでしょうか。
政府が、内部通報制度導入支援キットを作成し、300人以下の事業者向けにも体制整備をうながしていることは承知していますが不十分です。中小企業による体制整備を効果的に促進するため、政府は今後どのような手段をとることをお考えなのでしょうか、具体的にお聞かせ願います。
内部通報体制を整備することへの事業者のインセンティブ向上を図るため、平成30年から始まった内部通報制度認証については、令和2年改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討することとし、現在休止されたままです。認証制度では効果も上がらなかったのではないですか。現在の検討状況についてご説明いただくとともに、内部通報体制整備に対する事業者のインセンティブ向上のための施策についてどのように考えているのか、政府の見解を伺います。
私は、この法律が活用されることが、国民ひいては消費者の利益につながるものと確信しております。しかしその一方では、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報も事業者側から懸念されており積極的な活用の阻害となっていると考えます。EUの公益通報者保護指令には、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定もあります。濫用的通報の抑止に対する政府の取組について説明を求めます。
次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済について伺います。
改正案では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰として拘禁刑又は罰金を科す、法人に対しては法人重課の両罰規定を置くこととしております。
これにより、公益通報者の保護が一歩進んだことは評価しますが、内部通報後の組織内での嫌がらせ行為は、配置転換が主となっているのが現実です。しかし、配置転換については、メンバーシップ型の雇用慣行の下、事業者の裁量で頻繁に行われており、不利益性は個人の主観や事情に依存することを理由として罰則の対象にはなっていません。今後、我が国の雇用慣行が変わらない限り、配置転換に関する不利益取扱いに対する罰則や立証責任の転換は不可能とお考えでしょうか。政府の方針をお聞か
せ下さい。
最後に、今回の改正案では、事業者に対する行政措置について、現行法の指導・助言、勧告権限に加え、立入検査権や勧告に従わない場合の命令権などを新設。しかし、行政機関に関しては、自ら法令遵守を図り義務を履行することが期待されているとし、こうした行政措置については適用しないとされています。
前回の法改正後、国や地方自治体等、行政機関の内部通報体制や通報者の保護等が不十分だということも明らかになっていますが、こうした実態を踏まえても、行政機関に対しては、実態調査の実施、必要な助言や研修の実施等を通じて体制整備を促していくことで十分であるというお考えなのでしょうか。政府の認識をお聞かせ下さい。
公益通報者を保護することは、組織の風通しを良くし、自浄能力を高め、まじめに努力することが報われる社会の実現に資する、国民が安全で安心して暮らせる社会・国づくりにつながります。
政府がその原点に立ち返り、より良い制度を構築していくことを求めて、私の質問を終わります。

田村まみ国民運動局長(参議院議員/全国比例)は14日、国民民主党を代表し、参議院本会議で議題となった公益通報者保護法改正案に対する質疑を行った。質疑の全文は以下のとおり。
令和7年5月14日
国民民主党・新緑風会
田村 まみ
公益通報者保護法改正案
本会議質問
国民民主党・新緑風会の田村まみです。会派を代表して質問いたします。
ただいま議題となりました(公益通報者保護法)は、事業者による食品偽装事件やリコール隠し事件など、国民の生命、身体、財産等に被害を及ぼす可能性がある違法行為が相次いだことを契機として平成18年に施行され令和4年に改正法が施行されています。
令和5年11月に消費者庁が行ったアンケート調査では、従業員数が三百人超千人以下の事業者に勤務する就業者の57.6%、5千人超の事業者であっても47.7%が内部通報制度を理解していないことが明らかになりました。制定から20年以上が経過しているにもかかわらず、このように公益通報者保護法に対する国民の理解は未だ進んでいるとは言い難い状況にあります。国民の理解が進み活用促進される改正になるべく質問いたします。
はじめに、公益通報者保護法の周知・活用が進まない要因とされる、対象法律の範囲と規定方式について伺います。
公益通報者保護法の第1条は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することが目的であると謳っております。
故に、公益通報の対象となる法律は国民の生命、身体、財産等の利益の保護を直接的な目的としている法律に限定されております。
国民の理解が進まない背景には、法律の目的と対象法律が一致していないと国民から受け止められていることがあるのではないでしょうか。法律の目的を厳格に解し、対象法律を狭めていることから、結果として法律の活用と通報者の保護が進んでいないものと思われますが、伊東大臣に見解を伺います。
石破政権が中小企業の賃上げ環境整備に向けての施策の1つとして掲げる、企業間取引における適切な価格転嫁の是正に向け、下請法等の改正が審議されています。
下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用は、公益通報者保護法の対象法令です。その認識が中小企業や発注側企業の交渉担当者に周知され活用されることは取引の適正化に有用と考えますが、活用が進んでいるといえません。活用状況と今後の対策について、伊東大臣にお尋ねします。
赤澤賃金向上担当大臣に伺います。6月までに策定を予定されている円滑な価格転嫁を含む賃上げ支援策の議論の中で、この公益通報者保護法の活用について検討されていますか。
中小企業庁の下請けかけこみ寺への個別相談が身バレの恐れにより芳しくなく、価格交渉促進月間アンケート調査の回収率もいまだ20%に満たない状況です。伊東大臣、公益通報者保護法で保護される対象範囲の狭さが影響しているとは考えませんか。
公益通報者保護法を真に実効性のある法律にするためには、単に消費者被害の防止という観点だけでなく、法令遵守を促し、労働者を含む内部告発者を守る制度として位置付け直し、対象法律や通報対象事実を包括的に捉え直すことが求められているのではないでしょうか。先に挙げた企業間取引における法令違反は対象ですが、現行法の別表に記載の無い価格転嫁を阻害する商慣習等を威圧的に求める行為、いわゆるハラスメントなど、法令上明確な罰則規定がなくとも、公益通報の対象とする方向で検討すべきではないでしょうか。伊東大臣の見解をお聞かせ下さい。
次に、事業者が従業員等からの公益通報に適切に対応するための内部通報体制整備義務について伺います。以下、伊東大臣に伺います。
今回の改正案では、現行法の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしております。その一方、体制整備義務自体はこれまでと同様、常時使用する従業員数が300人超の事業者に限られ、300人以下の事業者については努力義務のままです。消費者庁の実態調査によれば、従業員数300人以下の事業者が内部通報制度を導入していない理由として、「努力義務にとどまるから」が48.9%と、最も多く挙げられています。
国民への周知を徹底するためには、従業員数300人以下の事業者による体制整備を義務化することが効果的だと思われますが、義務化は必要ないのですか、政府の見解をお聞かせ下さい。
小規模ゆえの人材を含む資源の乏しさから中小企業への体制整備義務化は困難という意見は承知しています。その課題への対応は、大企業と同じ形ではない手段を検討しつつ義務化を進めるべきではないでしょうか。
政府が、内部通報制度導入支援キットを作成し、300人以下の事業者向けにも体制整備をうながしていることは承知していますが不十分です。中小企業による体制整備を効果的に促進するため、政府は今後どのような手段をとることをお考えなのでしょうか、具体的にお聞かせ願います。
内部通報体制を整備することへの事業者のインセンティブ向上を図るため、平成30年から始まった内部通報制度認証については、令和2年改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討することとし、現在休止されたままです。認証制度では効果も上がらなかったのではないですか。現在の検討状況についてご説明いただくとともに、内部通報体制整備に対する事業者のインセンティブ向上のための施策についてどのように考えているのか、政府の見解を伺います。
私は、この法律が活用されることが、国民ひいては消費者の利益につながるものと確信しております。しかしその一方では、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報も事業者側から懸念されており積極的な活用の阻害となっていると考えます。EUの公益通報者保護指令には、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定もあります。濫用的通報の抑止に対する政府の取組について説明を求めます。
次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済について伺います。
改正案では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰として拘禁刑又は罰金を科す、法人に対しては法人重課の両罰規定を置くこととしております。
これにより、公益通報者の保護が一歩進んだことは評価しますが、内部通報後の組織内での嫌がらせ行為は、配置転換が主となっているのが現実です。しかし、配置転換については、メンバーシップ型の雇用慣行の下、事業者の裁量で頻繁に行われており、不利益性は個人の主観や事情に依存することを理由として罰則の対象にはなっていません。今後、我が国の雇用慣行が変わらない限り、配置転換に関する不利益取扱いに対する罰則や立証責任の転換は不可能とお考えでしょうか。政府の方針をお聞か
せ下さい。
最後に、今回の改正案では、事業者に対する行政措置について、現行法の指導・助言、勧告権限に加え、立入検査権や勧告に従わない場合の命令権などを新設。しかし、行政機関に関しては、自ら法令遵守を図り義務を履行することが期待されているとし、こうした行政措置については適用しないとされています。
前回の法改正後、国や地方自治体等、行政機関の内部通報体制や通報者の保護等が不十分だということも明らかになっていますが、こうした実態を踏まえても、行政機関に対しては、実態調査の実施、必要な助言や研修の実施等を通じて体制整備を促していくことで十分であるというお考えなのでしょうか。政府の認識をお聞かせ下さい。
公益通報者を保護することは、組織の風通しを良くし、自浄能力を高め、まじめに努力することが報われる社会の実現に資する、国民が安全で安心して暮らせる社会・国づくりにつながります。
政府がその原点に立ち返り、より良い制度を構築していくことを求めて、私の質問を終わります。